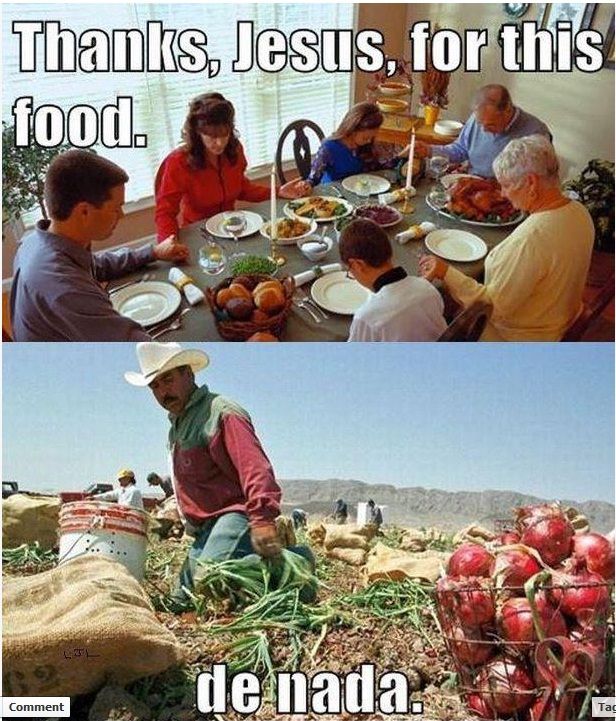日本では都知事選の関係で、「東京一極集中」vs. 「地方分散」の議論がネット上で飛び交っているようです。一方で、アメリカでは「都市回帰」が時代の流れになってきているな、という体感があります。
アメリカはもともと、土地が広くて人が分散している、というイメージが強いと思います。また、州の権限が強く「地方分権」の傾向も強くあります。ただ、それでも「都市」から「郊外」への分散というここ数十年の傾向は、そういったアメリカの「もともと持っている性質」とは違う力学が働いていると思います。
ひとことで言えば、1950-60年代の「モータリゼーション」です。当時、行政によるハイウェイの整備が進んだことと、石油メジャーによる石油/ガソリンの供給が増え、自動車産業がフル回転だったことの政治的関連は、よく知りませんが、まぁ間違いなくあったでしょう。この流れに乗って、大型トラックによる輸送の物流が中心となって、大企業が大量生産した食料や消費財が、郊外型の大型スーパーで大量販売され、ドライブスルーのファストフードが爆発的に増え、テレビでマス広告されるようになりました。人々は自動車を保有し、郊外の広い家に住んで自動車で通勤したり買い物するようになりました。
その結果、自動車を持てる中流以上の家庭と、持てない低所得家庭の間で、はっきりとした階級ができました。
例えばニューヨークでは、中心街のマンハッタンはビジネス街、そのすぐ外側で地下鉄で行き来できるハーレム、ブロンクス、クイーンズなどは低所得地域、ウォール街のプロフェッショナルなどは、さらに遠くの、自動車や料金の高い中距離鉄道でしか通勤できない、ウェストチェスター郡やコネチカットなどに住むのが普通です。(少なくとも、私が住んでいた90年代はそうでしたが、今はどうでしょうか?)
サンフランシスコでは、60年代公民権運動の時代に、「busing(バシング、バスで輸送する)」という、貧困地区の子供が富裕地区のレベルのよい公立学校に、スクールバスで通えるという仕組みを作りました。その結果、お金持ちが公立学校から逃げて学校全体が荒廃し、よほどのお金持ちなら市内の私立という選択肢もありますが、そこまでいかない中流家庭は郊外に逃げ出すことになってしまいました。
全米的にも、「都市内部(inner city)」というのは、「貧困地区」の代名詞となりました。
最近、いろいろなアメリカのシステムに歪みが出ているのは、こうした現在のエコシステムの大前提になっている「石油+モータリゼーション」というエンジンが、1970年代以降長期にわたって弱体化しているからです。一方で、90年代のネットバブルの時代に、シリコンバレーとウォール街に富が急速に蓄積し、その富を「都市」に投資して、荒廃したところをいろいろな手法で改造して美しくする「ジェントリフィケーション」が進行したり、環境対策や中東から輸入する石油に依存しなくてよいようにしようという米国政府の方針などもあり、特にわが地元のサンフランシスコでは「都市回帰」の傾向が顕著です。
少し前のブログに書いたように、列車・公共交通機関への注目が回復しているのも、その流れのひとつです。会社はシリコンバレーにあっても、住むのはサンフランシスコで、列車で通勤するというわけです。列車の駅の周辺は、以前はスラム街状態でしたが、最近は駅を改装し周辺に映画館やレストラン街を整備したオサレな「駅前繁華街」の建設が次々と行われ、いずれも大盛況です。私がシリコンバレーに引っ越してきたのが1999年で、その頃は子供を高速沿いのシネプレックスにアニメ映画を見に連れていきましたが、数年前にそこが廃止されて市内駅前の映画館に行くようになりました。今やリモートワークも普通にできるので、住む場所の選択肢も以前と比べてずっとフレキシブルになりました。
日本では、アメリカよりもやや遅れてモータリゼーションが起こりました。列島改造論は1970年代で、すぐに石油危機が来てしまい、列車の開発もその後も進んだので、アメリカほどのクルマ社会にはなりませんでした。それでも、あまりに東京になんでも集中しているために、今の都知事選候補の一人のように「地方分散」をポリシーとする人も多く、票田として大事なために「地方創生」なども行われています。
しかし、日本でも米国でも、もはや第一次産業に従事する人はごく少数しかいなくなり、「農地」に人を貼り付けていた時代のような人口の地方拡散はすでに不合理です。といっても、東京一極集中では産業のダイバーシティが実現しづらいので、私はいくつかの中核都市に異なる産業がそれぞれ群雄割拠しながら集中する「あちこち数極集中」が理想だと思っています。
サンフランシスコのジェントリフィケーションや都市回帰は、一方で以前から都市に住んでいた低所得住民が住むところを失うという摩擦も引き起こしており、このため住民がグーグルの通勤バスを妨害する騒ぎとなっています。何にせよ、すべてうまくいく話などないのですが、アメリカも日本も1950-70年代にできたインフラがそろそろ半世紀を経て老朽化する中、今のうちに都市にヘビーに投資する必要があると思っています。